ゴールデンウィークの休みを使って行った
DIYで基礎作りからやる木製フェンスの設置の顚末記です。
材料は、全てホームセンターで揃うもので行っています。
前回
伐採→穴掘り→基礎作り→支柱立て
ここまで終わりました。

今回は、その続き。
いよいよ、フェンス本体の作業に入ります!
材料選び
ホームセンターで材料を探してみたんですけど、フェンスの材料としてイケそうなのは、3種類ありました。
杉野地板・杉のディメンション材・ワンバイ材、この三つ。
杉野地板
杉がカットされたままの状態でその他の加工は特にされてません。値段は一番安いんですけど、ガサガサ感があります。
ワンバイ材

19×89mmの1×4(ワンバイフォー)材。SPF材とかいうやつですね。低価格なのが魅力的です。
杉ディメンション材

サイズはワンバイ材と同じ19×89mmで、杉を加工したものですね。野地板とは違い表面はツルツルした感じで綺麗です。値段はワンバイ材よりも若干高め。
で、この中から選んだのはワンバイ材。
ディメンション材と迷いましたけど、結局は値段の安い方を選びました。60枚以上は使う予定ですからね^^;
ちなみに、こういうものも売られていました。

こういうやつを使えば、かなりの時短になりますね。仕上がりもよくなるし。予算に余裕があるならこれも有りかもしれません。
あとは、桟木として使う胴縁材( 21×36mm )を購入しました。

作業工程
これからの工程は
- 支柱の補強
- 材料の塗装
- 桟木の取付
- フェンス材料の貼り付け
このような感じで進めていきます。
支柱の補強
支柱自体は基礎をガッチリ目にしたんで倒れる事はないと思うんですけど、フェンス材を貼りつけたら事情が少し変わります。
風をフェンス材がまともに受けますからね。
特にウチの場合、家の周りには風を遮るものが何も無いク○田舎なんです。

支柱が折れる可能性も全然あるんで、補強を入れることにしました。
立てた支柱に斜めに合わせて木杭を打ってやります。

この木杭は基礎を作りません。大ハンマーを使って気合いで打ち込むのみ( ・`ω・´)
固定は、12mmのボルトを使って行いました。

両サイドはボルトナットが木に食い込まないよう、座金は必須です。ガッチリと締込みます。
これで補強は終わり、ではありません。
斜めに打った木杭は、逆方向から強風が吹いた場合に浮いてきちゃいます。
なので、短い木杭を打ち込んで斜め木杭と固定してやります。

これで、支柱の作業は完了。
けっこう頑丈な出来になりました。少々の台風なら大丈夫そうです^^;
塗装
次に、購入した木材料の塗装です。

結構な量の塗装が待ってますw
私は塗装に関しては、ど素人。
どういう塗料が良いのかよく分からなかったんですけど、とりあえず適当に防腐剤入りの油性塗料を買ってみました。
色は濃い目のウォルナットというやつ。

基礎作りで手間取ったんで、この時点でゴールデンウィーク休みは残りわずか。
急ピッチで塗っていきます。
細長い材料ですけど、表・裏・側面とあるんで意外と手間取ります。

本来は二度塗りなんですけど、時間が無いんでとりあえず一度塗りで済ませました。
重ね塗りは、貼り付け完了後に行う作戦です。
桟木の取付
フェンス材料を貼りつける下地材の取付です。
丸い木杭のセンターにビス止め。

杭よりハミ出た部分はツライチでカット、カット面は後ほど塗装します。

丸い杭なので一直線に揃えて桟木を取付るのは難しいんで、段違いに取付けしました。
一直線の方が見た目いいんですけど、フェンス材で隠れるから目立たなくなるはず。そこらへんは許容範囲ということです^^;。
フェンス材貼り付け
最後の工程、塗装したワンバイ材を貼り付けてます。
ワンバイ材は 1820mm。これを二分割910mmの長さにして、縦並びに貼り付けていく予定
…が、ここで横やりが入ります。
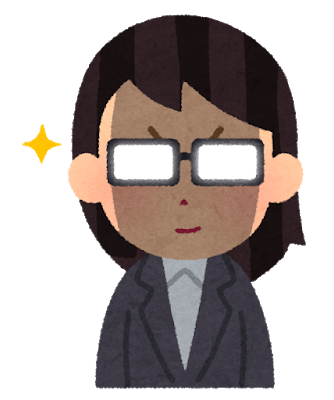
平坦に貼るより、アクセントつけた方が良いんやない?例えば山型に貼るとか…
「えっ…」
それって、めっちゃめんどくさいんですけどーっ
心の中で叫びます。決して口には出しませんw
逆らうとめんどくさくなるので^^;
結局、ワンバイ材を三つの長さに切り分けて順番に貼り付けていくことにしました。
ビスは32mmのコーススレッドで、直接止めです。
横の板と板の間隔は19mm。ワンバイ材を縦に挟んで隙間が等間隔になるように貼り付けを行ってます。

ちょっとしたアクセントですけど、平坦に貼るよりは少し良い感じにはなったと思います^^;
ちなみに、高さは支柱の木杭に水糸を張って合わせたんですが

高さ合わせは、何故か家にあるレベルを使ってます。

普通はレベルなんか持ってないと思うんですけど^^;
ちなみに、こういった機材が無い場合は透明なホースが有れば代用になります。
太さは細くて構いません。
一旦ホース内にエアが入らないように水を満たしてやって、ホースの両端部分を水が見えるくらい少しだけこぼします。
次に、ホースの両端を任意の位置に引っ張り、それぞれピン等で固定して水の高さを記していく。
これだけで水平は正確に合わせることが出来るんです。自然の原理を使ったやり方ですね。
まとめ
終盤は時間がなくてバタバタとした作業になっちゃいましたが、なんとか休み中にとりあえずの完成までこぎつけました。
とりあえず…というのはまだ庭の1/3しか終わってないから^^;
残りの部分も木の伐採からしなくちゃいけないんで時間がかかるんです。先は長い…
最後に反省点、というか、もっとこうすれば良かったなという部分についてですが
塗料や固定用のビスなどは、防腐防錆効果がしっかりしたものを使うべきだったな、とは思いました。
あまり深く考えないで材料決めちゃったんですよね、値段重視で^^;
ずっと風雨にさらされ続けるわけですし、けっこう重要な部分。もうちょっとよく考えておくべき点でした。
残りのフェンス作りの時は、もうちょっと工夫してやっていきたいと思います(^-^)
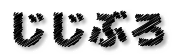




コメント